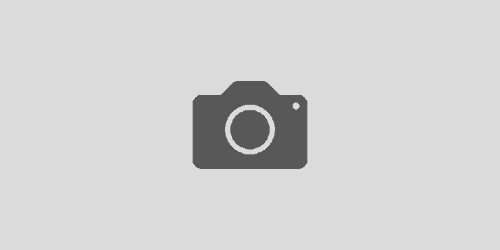積立NISAとNISAの違い及び両者の選択ポイント
2014年に「NISA(少額投資非課税制度)」が始まり、2018年からは新たに「積立NISA」がスタートしました。
両者とも、税制における優遇措置を受けられます。
ただ、両者を同時に利用することはできないため、どちらかを選択しなければなりません。
そのためには、両者の違いを認識しておくことが重要です。
積立NISAとNISAの違い
積立NISAとNISAの違いには主に以下が挙げられます(左側:積立NISA/右側:NISA)
1)年間投資可能額:40万円/120万円
2)非課税期間:20年間/5年間
3)投資可能総額:800万円/600万円
4)実施期間:2037年まで/2023年まで(2024年から新NISA)
5)取扱商品:投資信託のみ/株式・投資信託
非課税が適用される投資枠と非課税期間
年間の非課税上限額はNISAの方が有利ですが、ただ1年間に120万円も投資に回せる余裕のある家庭は限られます。
一般サラリーマンにとって、上限額の高さが大きなメリットにはなりません。
一方、非課税の投資総額で見ると、NISAの600万円に対し、積立NISAは800万円と多くなっています。
なお、NISAの非課税期間は5年であるため、5年目には商品を処分しなければなりません(ロールオーバーによって最大10年まで非課税可)。
一方、積立NISAは非課税期間が20年と長いため、長期的な観点で資金計画を立てられます。
また、20年という長さは、現役で働いている年数の約半分の期間で優遇制度を利用できることになります。
取扱商品と購入方法
積立NISAとNISAでは利用できる商品群が異なります。
NISAは株式と投資信託が対象になっており、利用者自身が任意のタイミングで、任意の商品を選択することができます。
一方、積立NISAは、金融庁が選定した投資信託やETF(上場投資信託)の中から選択しなければならないという制約を受けます。
また、「積立」であるため、同一金額で同一時期(毎週、毎月など)に商品を購入することになります。
まとめ
NISAと積立NISAは名前は似ていますが、内容は大きく異なります。
なお、その内容と性質から、両者では適する人が違ってきます。
NISAは投資資金に余裕があり、自分の裁量で投資をしたい人に適しています。
一方、積立NISAは運用よりも老後資金を確保したい人のための制度と言えます。
また、積立NISAは定期的に同じ商品を同じ金額で購入するため、ドルコスト平均法によって商品の平均単価が下がるメリットを得られます。
その結果、相場が大きく変動した時のリスクを低減化できます。